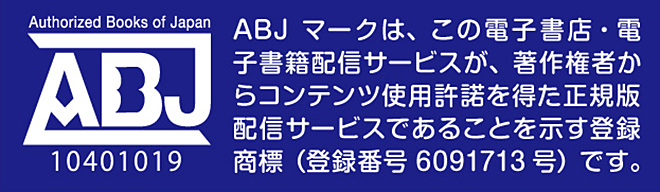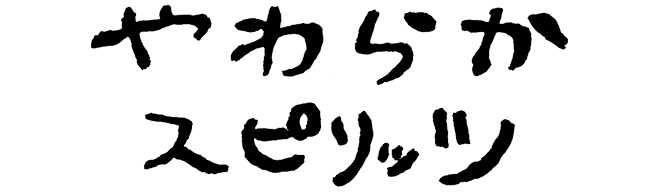2014.10.16
「他人事」にしがちな戦時下の暮らしを「実感」できる『あとかたの街』/【連載】深読み新刊紹介「読みコミ」(3)
コミックを長く「店頭」からながめてきた視線で選ぶ、
元・まんが専門店主の深読み新刊紹介。
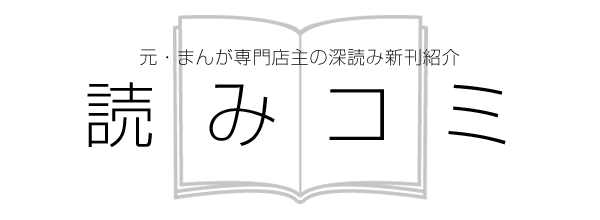
第3回『あとかたの街』第1・2集 おざわゆき(講談社刊)
「進め一億火の玉だ」と国が叫んでいた時代
でも私は自分が戦争に参加してるなんて気持ちはこれっぽっちもありませんでした
こんなモノローグで話は始まる。戦争末期の昭和19年、名古屋に暮らす12歳の少女・木村あいの家族の物語。
実父の体験談をベースに描かれたシベリア抑留記『凍りの掌』(小池書院・2012年)が高い評価を得たおざわゆき。この『あとかたの街』では名古屋に暮らす実母の体験談をもとに取材を重ね、戦時下の地方都市の日常を少女の目を通して生活感たっぷりに描いている。日本が戦争に突入した昭和16年(1941年)、そして昭和20年(1945年)に迎える敗戦。この頃の実感を伴った記憶をキープできている人は年々少なくなっている。主人公のあいも含めて、10代で戦争を体験した大正末期~昭和初期の生まれの人たちの現在年齢はざっと80歳~90歳。その下の昭和10年代生まれ(70歳代)になると戦争は幼少期の記憶でしかなく、戦後=昭和20年代生まれにとっては別世界、さらに後の生まれとなると戦争はもう異次元での出来事だ。知っているような気がしているけど実は知らない、知らされる機会のほとんどない世界、それが戦時下の世界。そこはいまの常識に照らせば桁外れの理不尽がまかり通っていた世界でもある。それもまた日本。「足並みをそろえよ!」と食べるにも汲々とする貧乏世帯にまで国債の購入を迫る婦人会組織。「動員され働くことは学問することと同じである」という文部省が打ち出した理念のもとに始まる女生徒たちの工場労働、等々。それらを人々が暮らしの中でどんなふうに受け止め、受け入れていったのか、登場人物を通してなら実感できる気がする。それは読者が登場人物たちの「感情」にコンタクトできるからだろう。その世界で生きるという"他人事"を"実感"に変換するアダプターがこの「感情」なのだ。第1集P.160~P.161ではページをめくる手がしばらく止まる。主人公の視野に映るこの光景を、平成26年に暮らす我々はイマの光景のように錯覚することができる。歴史と現実の距離、その遠近感。少し想像を巡らせるだけで、ああ、きっとこんな感じなのだ......と体感できるものがある。


『あとかたの街』第1・2集 おざわゆき(講談社刊)
第2集では、情報統制のもとで大事なことを知らされることなく暮らし続ける人々を、大地震、そして度重なるB29による爆撃が襲う。暮らしの場を壊し、命そのものを奪いにやってくる「空襲」。受け止めようのない圧倒的な暴力に多くの人々がなすすべもなく殺されていく。でもそこで死ぬのは"多くの人々"と呼ばれる無名集団ではなく、自分の子だったり、兄弟だったり、友達だったりするのだ。そしてそれは、自分であったりもする。P.162~P.163では時間がゆっくりと止まる。目の前の、空から落ちてくる爆弾と自分との距離を想像してみる......自分の時間のすべてが止まる瞬間を想像することは、たやすいことではない。
戦時中の"事実"をより"実感"に近いものに変換し伝えることのできる媒体としてマンガはとても適していると、この作品を読んであらためて思った。知識と情報だけでは捉えられない世界に想像力を加えることで、そこに生きた人の実感の尾に触れることができる。過去を現在の都合に合わせて解釈するのではなく、過去は過去のままに飾ることも歪めることもなく認識するという姿勢が、過去とその時代に生きていた人たちへの礼儀正しい接し方だろう。読者が『あとかたの街』を読んで抱く共感にはきっと、そんな戦争の時代を生きた人々への作者の誠実なスタンスに対する共感も含まれているのだと思う。
南端利晴(元・まんが専門店主)
【初出:コミスン 2014.10.16】
あとかたの街,おざわゆき,読みコミ,連載