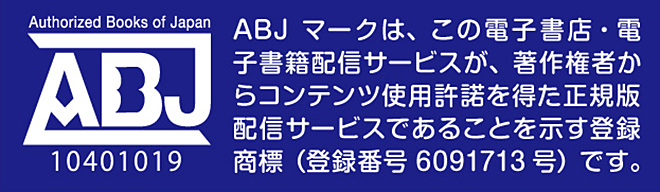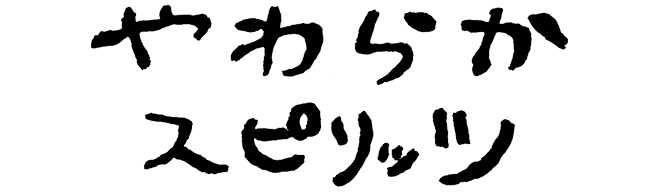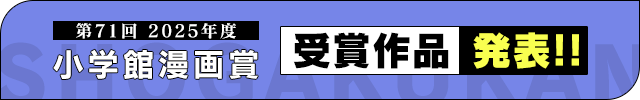2022.10.24
第二回スピリッツ新人王開催記念 大童澄瞳氏インタビュー 前編
<その1・プロフィール編>
ビッグコミックスピリッツの月例新人賞「スピリッツ賞」をリニューアルし、始まった「スピリッツ新人王」。半期に一度、最前線で活躍する漫画家さんが審査員長となり、最も面白い投稿作を決定する今賞。第二回審査委員長は、アニメーションを通じて“最強の世界”を実現するべく奮闘する映像研の面々の活躍を描いた大ヒット作『映像研には手を出すな!』作者・大童澄瞳(おおわら・すみと)氏。
前編となる本項では、同人活動から漫画制作をスタートしスカウトされたことから漫画家としてデビューすることになった大童氏が、右も左もわからない世界で、編集者と共に自分の描きたい世界を構築していき、やがて大ヒット作品『映像研』を生み出すまでに至る話をうかがいました。
(インタビュー=田口俊輔)

Q.大童さんが初めて本格的な「漫画」を描いたのはいつ頃だったか覚えていらっしゃいますか?
初めてのストーリーがある漫画『ウサゴギ』を、コミティアに向けて描いたのが最初です。『映像研には手を出すな!』第1集のプロフィール欄に「2015年、コミティア111に出品」と書いてありますね……そうだ、コミィティア110が初参加で、コミティア111で編集者の方に声をかけていただいたんだ。コミティア110の開催年が2014年、ということは21歳の頃に初めて漫画を描いたことになりますね
僕はコミティアに出店する以前まで、一人でアニメーションを作っていたり、絵画の専門学校に通うなど、絵はずっと描き続けていたのですが、『ウサゴギ』まで“漫画を描く”ことは、ほぼ経験していなかったんですよ。せいぜいあったとしても、子どもの頃に描いた、一枚絵の中にちょっとストーリーが箇条書き程度で書いてあるもの程度で。
そもそも僕は、学生時代から「絵にまつわる仕事」……可能であれば、アニメーション周辺の仕事に就ければいいなと思いながら、その業界を目指して活動していました。そのために絵画の専門学校に通いファインアート(絵画や彫刻など美術の総称)を学ぶのですが、その理由も、「もしアニメーションを作る才能がなかったとしても、絵コンテを描ければ制作に携われるはずだから、基礎的な画力を向上させよう」と、あくまでアニメ作りのためのもので。
卒業後、そういえば本格的なアニメーションを自分で作ったことがないなと気づき、「一年かけて一本作り上げよう」と、一人でアニメ作り始めるのですが、結果は10分ほどの短編を作る予定のところ2分ほどしか作れず(苦笑)。1年かけてこのペースは難しいなと思い、その他のお話がある絵を使った表現とは何か?と考え、漫画があるなと思いついたんです。
よくよく考えればアニメーションは10枚や12枚ほど描いて大体1秒になるところ、漫画はページ1枚描けば、数十秒から数十分のストーリーを語れてしまう。それならば都合がい、とりあえず一つ形にしてみようと描き始めた、という流れです。
Q.各漫画媒体には今回の新人賞のような賞レースや持ち込みなど、様々な形でのデビュー手段が用意されています。あえて同人活動から始めると選択されたのは、意図があったのでしょうか?
漫画を描いてみるものの、「漫画家になる」という選択肢が、当時の僕にはなかったんです。とりあえず自分の作品を作り、それが世に出て、どんな反応を得るのかを見たいと、発表の場としてコミティアを選んだのが正直なところで。そうした持ち込みや新人賞への応募などは、自分が漫画家を目指しているという意識がなかったから選択肢に上がらなかっただけなんです。
そもそも『ウサゴギ』を描いてコミケに出す時点では就職活動を始めていて、そちらへと比重が傾いていたので、「いつか『ウサゴギ』が、僕の目指す何かに繋がればいいな」ぐらいの気持ちだったんです。コミティアの会場で小学館の方にスカウトしていただいたときも、全然漫画家になるんだという意識へとシフトしていけませんでした。
どういう流れで漫画が連載に至るのか、という事を調べてみたりしたのですが、「担当編集がついて、新人賞で入賞して、連載会議へ」というような通常のプロセスと違い、僕の場合はいきなり連載会議だったので、自分がどのような状態にいて、どのように進んでいるのか、あまりよく分かっておらず、ほぼ言われるがままでした。
しかも、連載に向けての準備期間は、漫画を描いてもお金が発生しないので、「このまま連載会議に通らない状況が長引き、上手くいかなかったら、一度この話は引っ込めよう」と考えていました。ただ、ずっと「絵を描いて仕事にする」という憧れがありましたし、別に失うものは元からない状態でしたので、この経験が何かの形になるなら、このまま進むのがいいんだろうなとは思っていました。
Q.スカウトされてから実質、1年ほど編集者との打ち合わせやプレゼン会議を積み重ねながら『映像研に手を出すな!』に辿りつきました。全てが初めての中、大童さんは担当編集者の方と、どのようにプロセスを積み重ねていき今作の執筆にたどり着いたのでしょうか?
『ウサゴギ』を描いた時点では、自分の絵もストーリー構成も、いわゆる“王道”ではないという自覚がありました。なので「商業媒体で描く」という重要なポイントを知るためにも、自分の作品がどういうプロセスで売れていくか?を確認するっていう意味でも、どのようにして・どういった作品を売っていくかのノウハウを持った編集者さんの意見を仰ぐことから始めました。
いかに作品を売っていくか?の話を聞いたところ、最初は、「既にファンのついている界隈に向けたお話を作ってみてはどうか?」と、提案されました。 例えばガンダムという巨大なマスに向けるとしたら、ガンプラを題材にした話、オリジナルストーリーを展開する、なんならガンダムを好きな人の話でもいい、とにかくガンダムが好きな人に向けて作品を作る。あるいは鉄道なら、乗り鉄の話、撮り鉄の話、模型……と、既に業界に多くのファンがついている題材で展開すれば、まだ名前を誰も知らないような作家でも手に取ってもらいやすいと話をうかがいました。
なるほど、そうした売り方があるんだ!と知り、まずはそこから始めてみようと、自ら興味を向けられる大きな題材として、上がったものが『ドラえもん』でした。なので、最初期は『ドラえもん』にまつわる漫画を連載会議に向けて描いていました。ただ、作品を提出したところ、内容は面白いけれど、毎回大量に登場する秘密道具の裏話をチェックするのは大変だと、藤子プロ内部で評価が真っ二つに分かれてしまったそうで(苦笑)。結果的に『ドラえもん』を題材にする話は流れました。まあ、今思えば、『ドラえもん』には非常に膨大な知識を持ったコアなファンが大勢いるので、そこに自分が乗り込むのは厳しかったでしょうね。
その後に、改めて一から考え直そうと、ゼロからオリジナルの話を考えていくことになりました。
この時に僕の肌感覚として、SNSの発達によって、プロからアマチュアまで「“チャレンジしたい”クリエイターの数が今までになく増えているな」という実感があったんです。そうしたクリエイターの投稿に対する大きなバズを見ていると、クリエイターに向ける視線が社会の中で大きな割合を占めるようになっていて。ひいてはクリエイターの労働問題も表沙汰にされるようになってきた。
映像投稿のSNSや動画投稿サイトも爆発的に増えてきている今、個人が映像制作する状況を描いた作品はどうだろうか?と編集者さんと話し合ううちに、『映像研』の雛形が徐々に固まっていったという感じです。
Q.以前、別のインタビューにて、執筆当初は大童さんが高校時代に実写映画制作の経験があるから、実写映画制作をベースにした展開にすれば、話が膨らみやすくなるのでは?と編集者に勧められたと語られていましたね。
そうなんです。最初は、実写映画を軸にした映像作り全般のストーリー構成で行こうとなりました。登場人物が映像を作っていくという物語の流れの中で、映像制作に関わるノウハウが語られていく……という展開にしようと、まず描き始めました。
その時に描いた第一話目の流れは、今の浅草氏に相当するキャラクター……確か当時から名前は「浅草」だったと記憶していますが、友だちがいないため自分一人で映画を作ろうとするというシーンから始まって。そこで、カメラの首振りをしようとするのですが、カメラのパンは一人の力ではできないんです。ならば、その首振りナシで実写映像は作れるのか?というチャレンジから、物語が展開されていくというものでした。
一通り思った通りにものを描き終え、担当さんに見せたところ、「確かに面白いけれど、アニメの方が今人気のイメージがあるので、後々実写での制作やクレイアニメなどの手段を題材にしてもいいけれど、第一話での試練はアニメーション制作を軸に語れないだろうか?」と言われたと、記憶しています。
そのアドバイス通り、アニメーションの制作過程を最初に持ってきたところ、「このまま、アニメーション制作を軸にした漫画が良いんじゃないでしょうか」と提案され、アニメ作りだけで1本いくんですか!?と驚いて(笑)。正直、僕としては「それで、大丈夫かな?」という思いつつ、編集さんの振りきった提案から『映像研』の企画はスタートしたんですよね。
ただ、こう提案されつつ、どこかで読んだ受け売りですが「編集の言ったことをそのまま漫画にする作家は二流だ」という教えが頭の片隅あったため、編集者さんの意見を全部鵜呑みにしてやるぞ!というつもりは、一切ありませんでした(笑)。
Q.そうした意識から始まった『映像研』。物語を作り上げていく中で、大童さんにとって譲れないものと、編集の方の意見で擦り合わせが出来ずに、いわゆるぶつかり合いのようなものはありました?
ん~ 自分のやりたい表現を崩さずに、編集者の意図を汲み取りながら上手くその間を作っていくそのぐらいじゃなきゃ駄目だと最初から意識していたので、ぶつかり合いはありませんでした。ただ、意見の擦り合わせの中で、いろいろと考えることはありました。
たとえば『映像研』の中に、劇中で登場する機械やキャラの設定が見開きで出てきたり、空想の世界に飛んでその世界に入り込んだ状態でキャラクターたちがメカを作る場面などが出てきます。これは『映像研』の中でも特に特徴的なシーンだと思いますが、この場面や流れが生まれたのは訳があるんです。
第一話で浅草氏と水崎氏が、共同作業で作品世界を作り上げていくシーンがあります。連載時には二人が相当な熱を持って、“最強の世界”を作り上げていく場面になっていますが、初期はかなりアッサリした描き方をしたんですね。
なんと言いますか……“クサい表現”があまり好きではないタイプでして、当時はもっと今以上にその傾向が強く、「何か一つのものを共同で作る作業とは、ひたすら淡々としていて、かなりアッサリしたものになる」と考えていたので、非常に盛り上がりという意味では静か場面として描いたんです。
ところが編集さんがその場面を読んで、「ここはカタルシスというか、ワッ!と二人で情熱を持って作っていき、最後に完成してヤッタ~!みたいな形にしてくれると、すごく多くの読者に響く形になるんですが」と、提案してきたんですね。それを聞いた僕としては、「絶対やりたくない!」と拒否反応を起し、悩んでしまったんです。
とはいえ、売ることのプロがそうおっしゃるわけです。では、“クサい演出”をせずに、読者に響かせて、編集者さんが僕に提案した内容を達成するにはどうしたらいいだろう?と考えに考えて。一つ出した答えが、「これは小学生ぐらいの頃からやっていた、“ごっこ遊び”の延長線を描けばいいんじゃないか?」というものでした。
感動的なシーンではなくただ、ひたすら「作るの、楽しい!」っていう気持ち。「妄想することって、ただ楽しいだけだよね」という、その気持ちをそのまま絵にすれば、人にもストレートに刺さると思いついたんです。なので、設計図や設定画のようなものをそのまま載せて、妄想の世界でバリバリと飛行機を作っちゃうという表現を入れ込めば、“クサさ”を極力抑えながら、盛り上がりも生み出せるなと。
その後も編集者さんからは、熱いものや青春っぽい描写が求められていたと思うんですけど、その編集者さんが求めたものを噛み砕いた結果、「要するにすごく楽しくて、カタルシスがあればいいんだよね」と、自分の中で納得できるものに置き換えていきました。

▲(『映像研には手を出すな!』1集より)
Q.その大童さんが編集の方の意図をくみ取り、自分の表現へと昇華できる能力は、なかなか新人作家が最初から持ちうるものではないと思います。お互いの考えを上手く折衷し作品を生み出す能力は、どのように醸成したのでしょう?
僕の家系が文系で、いつも家族間でテーマを決めて議論するということを度々していた影響があるのかなと。意見の対立=敵対関係ではない、意識の食い違やのは全然悪いことじゃないと承知しながら生きてきたので、考えの擦り合わせにかんしてはそこまで難しいものではありませんでした。
あとは、ちょっとしたバイトとして、編集者・漫画原作者の竹熊健太郎さんが多摩美術大学で教鞭を執っている、「漫画文化論」という漫画やアニメについての講義の手伝いをしていたことも大きくて。その授業では、前期と後期で受講生たちから漫画を提出させるっていう課題があって、非常に人気の授業のため年間600本ほどという膨大な数の漫画が集まるんですね。
そこで1、2年ほど、竹熊さんと一緒に生徒から上がってきた漫画を確認する手伝いをしていて、竹熊さんが「この作品はすごい」と褒める一方で、「これはちょっと意味わからないな」と言っているのを横で見ていたんです。
竹熊さんは編集者や原作者として数々の作品に携わったり、現在もWebで「電脳マヴォ」のような漫画家を目指す人をバックアップする媒体を運営されたりと、漫画を評価する手腕がものすごくある方なわけです。バイトの中で、「漫画の読み方」の視点に少しだけ触れていたのも大きかったんだと思います。
Q.そうして編集者が求める編集者との二人三脚で作品を作り上げていく中、大童さんにとって今でも忘れられない、今でも大きな指標となっている、人からの言葉などはありますか?
何のノウハウもないときに編集者さんに言われた「なんでですか?」という言葉は、かなり大きかったですね。
例えば水崎氏が(ロボットアニメ制作時に)、「私はチェーンソーの刃が跳ねる様子を観たいし、そのこだわりで私は生き延びる。大半の人が細部を見なくても、私は私を救わなくちゃいけないんだ。」というセリフを言います。この一言は「アニメ作りの際のこだわりこそ自分の源であり、徹底して細部を描くことは自分を助けるためだ」というニュアンスのセリフなのですが、最初はこのセリフを言う前に説明をつけなかったんです。
すると編集者さんから「なぜ、この子はこんなにアニメーションの表現にこだわるんですか?なんでですか?」と、詰められてしまって(笑)。僕は読めば理解してもらえると思っていたので、「実はこうした理由があって……」と説明すると、「では、その説明をちゃんと描いてください」と、ハッキリと言われてしまったんです。
この「感情をセリフで表すと、それだけ多くの読者に届く作品になる」という教えは、自分の中にはなかったものなので、それは一理あるなと学びました。ただ、僕としては、先ほどの“クサい表現”が苦手というのに加えて、この「セリフで感情を説明する」というやり方についても苦手で。「そう描かない手もあるんだよ」とは、ずっと言い続けたいなと思っています。まあ、描かない代わりに売れない可能性もありますが(笑)

▲(『映像研には手を出すな!』2集より)
Q.逆に、これは自分の身にならないなっていう教えもきっとあったと思います。
僕にとってですが、「女の子を可愛く描けると結構いいんですけれどね」という教えは刺さりませんでした。そもそも僕は『映像研』のキャラクターは、みんな可愛いと思って描いているのが大前提にあって。
まず“可愛い”の表現の仕方をどう受け止めるか?って人によって違うはずなんです。動物的に可愛いのか?それともラブコメのヒロイン的に可愛いのか?他にも言い表す言葉があれば明確に分類できるぐらい、“可愛い”の種類っていろいろとあると思うんですね。僕の場合は前者の「動物的に可愛い」方がすごく魅力的だと思っていて。
食べ物で例えるとするなら、工夫してか色んな野菜を何日間も煮詰めて出汁を取ったラーメンより、町中華のあっさりしたラーメンの方が大好きで。その街中華のラーメンのようなキャラクターを作りたい僕からすると、編集者さんの目指す方向は結果的に参考にはなりませんでした。
Q.こうして誕生した『映像研』は大ヒット作になり、アニメ化・劇場映画化もされ、とてつもなく幅広い層へと届いています。ただ、『映像研』ではたびたび、「作ることの喜び」と同等に「人に伝わる作品作りへの葛藤と難しさ」について深く掘り下げているなと拝読しながら思っています。これは大童さんとして、『映像研』を通じて伝えたいメッセージなのでしょうか?
ん~……大きくあるわけではないのですが、この「人に伝える事」の難しさは、確かに自分の中ですごく大きいですね。というのも、漫画連載の経験は『映像研』が初めてですし、そもそも漫画家を目指していたわけでもなかった。それ以前も、アニメーションを作り上げられなかったし、『ウサゴギ』も完結していません。物語は王道ではありませんし、絵柄も今一番人気がある絵柄とはかなり違う上に、人の絵の模写などもあまりしてこなかったタイプなので、本当に長い間「はたして自分の作品は、人に届いているんだろうか?この描き方で読者はわかるんだろうか?」という葛藤がありました。
作中で浅草氏が、アニメーションを作るにあたって、「自分の作品がどういうふう届き、どういうふうに人に見られているか?」と心配し葛藤するのは、本当に僕自身の悩みでもあるんですよ。
なので、最近では自分が『映像研』を描いている上での“言い訳”を、とにかく『映像研』の中で描くことを繰り返していて。特に最近の単行本(第7巻)にはその“言い訳”が色濃く出ています(笑)。「自分の作品が読者に伝わるかどうか?」という葛藤と、それに向けての答えをとにかく描き続けている作品と考えると、僕は……強いて言うなら「みんな、いろいろと考えながら作品を作っているよ」ということ、を伝えたいのかもしれません(笑)。
あとは、そうだな……『映像研』の中での表現とは少し反れたところですが、「別に友だちなんかいらないじゃん」ということを、描きたいという想いはありますね。多様性のようなものを表現したいわけではないのですが、「世界にはいろんな人がいるよ」ということを、この先も描いていきたいなとは思っています。
(後編につづく)