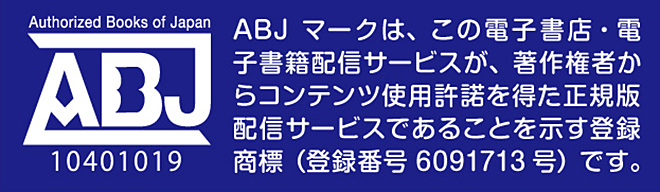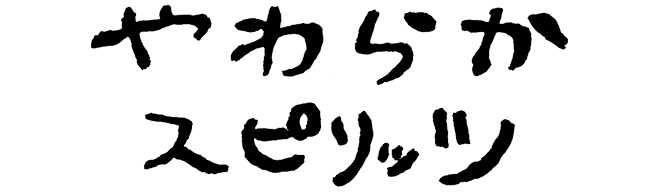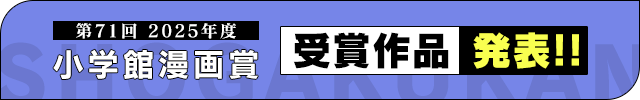2018/07/30発売
花男 満塁ホームラン
松本大洋
「花男」は松本大洋の最高傑作だ。そう断言する。もちろん、一作毎にテーマに沿って
画風を変え、新しい境地を目指して進化する彼の、このほんの初期作品が最高到達点の訳はない。だが、いうなれば入団2年目の投手が達成した「完全試合」。そんな意味での最高傑作なのだ。連載終了直後に、おそらく極度の緊張から解放された為だろう、鬱状態に陥ったというのもその証拠。無理もない。
さて、その「花男」の裏話と言えば、「次は野球を描きますよ、だって堀さん、野球、バカみたいに好きでしょ」という松本大洋のぐっとくるいいセリフとか、「僕は、昔、あの辺の高校の4番打者で連載当時はなりたての父親でした。だから花男のモデルは僕と言っても・・・」という、僕自身のしょうもない自慢とか、「カッパとか天狗とか、いらないでしょ。ない方がすっきりするでしょ。あと、口の中、奥歯の溝まで描いてなんか気持ちいい事あるの?」という、校了者たちからの心ない?指摘との戦いとか、数々あるのだが、どれもこれもささいな出来事のように感じられる。
連載中、僕がずっと感じていたのは、幸福感だ。この作品の第一読者であることの。まさに真の意味でのnew waveに立ち会えていることの。毎週、毎週あんなに楽しく仕事をしていたのはあの年が一番かも知れない。(結婚もしたしね)
なぜあんなに楽しかったのだろう? それは「花男」がハッピーに彩られてハッピーエンドに至る道を、余計な外連を差し挟まず、只ひたすら邁進している作品だからだ。一歩間違えれば都合のいいおとぎ話になりかねない設定、時系列や地理的関係や距離はいささかご都合主義、でもそんな事をものともせず、父と息子と夏と野球は、歯切れのいいセリフ群、最新鋭の描写、構成という松本大洋の漫画力にささえられ、普遍的かつ唯一無二の父子モノに昇華したのだ。
古今東西、父と息子の話は数多ある。本人もある映画から着想を得たと語っている。しかし、「花男」は父親の存在感、無敵性において、他の追従を許さない。ん?何かあったぞ。
花男に匹敵するくらいの父親が出てくる作品が・・・
「天才バカボン」だ! 気づくと全てが繋がっていく。バカボンのパパは花男と同じく職業不詳のくせして、家族を持ち養っている。バカボンのママは花織さんと同じく、なぜこの男と結婚したか分からない、よくできたいい女だ。バカボンは、茂雄と同じく・・・バカじゃないな。いや、茂雄はハジメちゃんとして生まれ、バカボンへと進化する複合体なのだ。
決定的な証拠を挙げよう。連載初期のバカボンは自分がバカだと自覚している。ハジメちゃん誕生を目前にひかえ、こんなんではちゃんとしたお兄ちゃんになれないと悩む。そこに、救いの手を「これでいいのだ」と差し伸べるのが、無論、パパなのだ。「バカボンはバカボンのままでいいよ」と。一方、天才を装っていた茂雄は、花男の「感じろ、吠えろ、ビリビリしろ」との叱咤激励の呼び声に、最終的に応える。自分の中の花男性、バカボン性に目覚めるのだ。ほっぺににも心なしかグルグルが浮かんでいるようだ。みごとに父と息子のユートピアが両作品に誕生する。
でも、この父と息子のユートピアは、実際の世界ではもちろん、漫画でも一瞬の夢だ。不世出の天才、赤塚不二夫は自らの手で幸せなバカボン家を、シュールなギャグの世界に塗り替えて跡形もなく消し去ってしまう。一方、われらが松本大洋は、どうしたのだろう。「Sunny」がその答えなのかもしれない。哀しい境遇の子供達のクールな日常を描いたこの作品にユートピアは登場しない。しかしそれ故、登場人物達が普遍的ユートピア、各々の唯一無二のユートピアを信じている事が浮き彫りになる。それは、すなわち松本大洋が自らの作り出したユートピアを信じている証左だろう。
良かった。やっぱり「花男」の世界は、あの理想の海辺の町で今でも健在なのだ。カッパも天狗も、カバもワニも、もちろん花男と茂雄も声を合わせて叫ぶのだ。
「ビリビリしたァ!!」「ビリビリしたかあっ。」